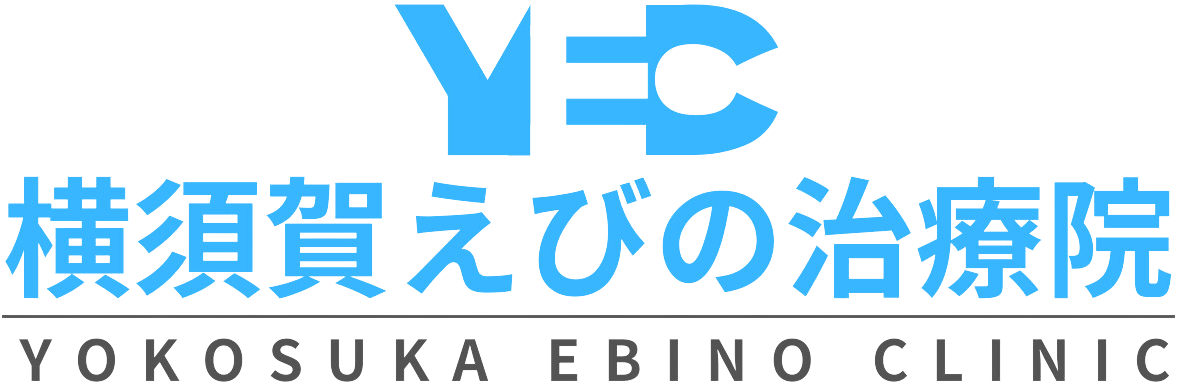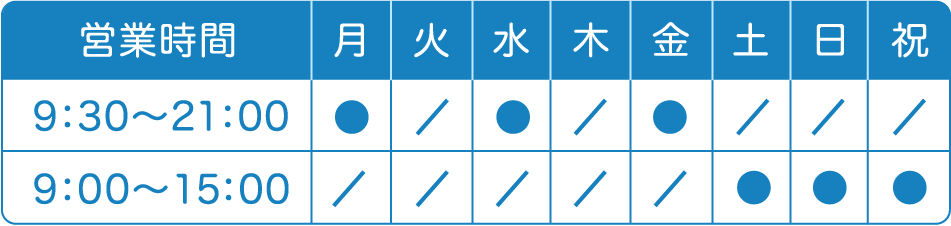痛みの定義
「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験かつ個人的な体験」
この定義は、痛みが単に「痛い」と言う感覚だけではなく、それが感覚的・情動的な体験であることを伝えています。
さらに、痛みは「実際の損傷」や「損傷のリスク」と関連し、それらの感覚がどのように知覚されるかについても記載しています。
つまり、組織の損傷があってもなくても「痛い」と言う感覚は感じることがある。
と言うことを伝えています。
痛み学基礎2では、痛みの定義の内容を深掘りして、我々がどのようにして「痛い」と言う感覚を感じるのか?をお伝えしていきます。
内容は少し難しいですが、何度も読み返してしっかりを理解を深めていってください。
「痛み」を知ることが、あなたの体の痛みを取る第一歩です。
実際の組織損傷による痛み
痛みは、「組織損傷」に伴って生じる感覚であるという点が最も基本的な部分です。
身体に外的な傷害や損傷(例えば、切り傷、骨折、炎症など)が生じると、その刺激が痛覚受容器に伝わり、その信号が脊髄を経て脳に到達し、痛みとして知覚されます。
実際の損傷
これには、体の一部に外部からの物理的な力が加わること(例えば衝撃や圧力)、または内部で異常が発生すること(例えば炎症や感染症)が含まれます。
ノシセプション
実際に組織が損傷を受けることで、痛みを感知する痛覚受容器(ノシセプター)が活性化し、神経伝達が脳へ送られます。この信号が脳に届くことで痛みとして認識されます。
ノシセプションとは?
ノシセプションは、「避難行動」のようなものだと思ってください。あなたの体には、「危険を察知するセンサー」があります。
危険を察知するセンサーを「ノシセプター」と言い警報装置のようなものだと思ってください。
これらのセンサーは、体に何か危険が迫ると、それをいち早く察知して脳に伝える役割を果たします。
警報装置が作動して、その情報が届くことで、我々は避難行動に移すことができますよね?
痛いという感覚も同じで、体の警報装置からの情報が脳へ届くことで体の異常に気づくことができるのです。
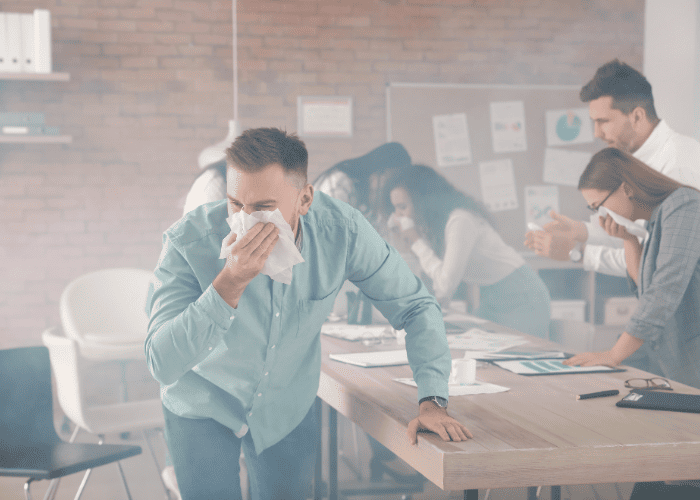
熱い鍋を触ったとき
例えば、熱い鍋に触れたとき、手にあるセンサーはその熱を「危険だ!」と感じ取り、すぐに脳に信号を送ります。
この信号が脳に届くと、脳は「これ、火傷になるかも!危ない!」と感じ、痛みとして「手を引け!」という警報を鳴らします。
この一連の流れがノシセプションです。体が感じ取った「熱さ」という危険信号が、警報のように脳に伝えられ、即座に反応を引き起こします。
熱い!痛い!と言う感覚がなければあなたの手はこんがりと焼き上がってしまいます。
転んで膝を擦りむいたとき
転んで膝を擦りむいた場合、膝にあるセンサーが「おっと、皮膚が傷ついている!これは危険だ!」と感じ取ります。
この時も、センサーは危険を察知する警報装置のように、すぐにその情報を脳に送り、「膝が傷ついてるよ!痛みを感じて、すぐに対処しよう!」という警告を脳が出します。
脳はその警告を受けて、痛みとして感じ、体に「手当てをしよう!」という指示を出します。
この痛みの感覚がなければ、膝の傷に気づかず血だらけのまま歩くことになるでしょう。
冷たい水に手を突っ込んだとき
冷たい水に手を突っ込むと、手のセンサーが冷たさを感じて「危険かも!長時間冷たいものに触れていると凍傷になるかも!」という警告信号を脳に送ります。
この警告はまるで冷水を触ったときの「冷水警報装置」のような役割を果たし、脳は「これ以上冷たい水に手をつけないように!」と警告します。
痛みを感じさせることで、手先の凍傷が起こらないように体を守ろうとするのです。
警報装置の重要な役割
この「警報装置」は、危険があることを知らせるために非常に重要です。
体が実際に損傷する前に、「ノシセプション」が働くことで、私たちは早期に反応し、体を守ることができます。
警報装置が正常に働いてくれることで、我々が避難行動(ノシセプション)を取れる思えば、痛みを感じるプロセスが理解しやすいかもしれません。

「組織損傷が起こりうる状態に付随する」とは?
この定義は、痛みが「実際の損傷」の有無にかかわらず、損傷のリスクやその予測に関連しても生じる可能性があると言うことを示しています。
潜在的な損傷
例えば、過度の筋肉の緊張や不適切な姿勢が長時間続くことで、痛みが発生することがあります。
この場合、実際に組織が損傷していないものの、その損傷が「起こる可能性」があることが、痛みの発生に関与しているという事になります。
皮膚をつねった時に痛みを感じるなどがイメージできると思います。実際に皮膚が捩じ切れる前に痛みを感じるから、それ以上強い力でつねることはないということです。
また、予防的な警告信号として考えることもできます。
前項で解説したノシセプションはこれらの予防的な痛みに大きく関与しています。
「痛み学基礎1」の復習はこちら→
体が損傷する危険性がある場合(例えば無理な動きや姿勢を続けること)、痛みが「警告信号」として発生します。
これにより、体は無理な動きや姿勢から逃れることができ、組織の損傷を防ぐ役割を果たします。
体が硬い人がストレッチをすると痛いと思いますが、まさにこの予防的な警告信号といえます。
「感覚かつ情動の不快な体験」とは?
痛みは、「感覚的」な側面(身体的な不快)と「情動的」な側面(心理的な苦痛)の両方を含んでいます。
痛みには二重の側面が存在します。この定義は、痛みが単なる感覚的な反応にとどまらないことを伝えています。
痛みは、生理的な信号としての「感覚」と、それに伴う「感情的反応」の二重の側面を持っています。これにより、痛みは非常に「主観的」で「個別的」な体験となるということが言えます。
感覚的な側面
痛みは身体的な不快感として知覚されます。
圧力や熱、切り傷などによって引き起こされる生理的な反応により不快感を感じます。
不快感は、鋭い痛みや鈍い痛み、焼けるような痛みなど、様々な質で感じられます。
情動的な側面
痛みに対する感情的な反応(恐怖、焦燥感、悲しみなど)が痛みの強さや耐性に影響を与えます。
痛みは感覚的な不快に加えて、強い「感情的反応」を引き起こします。
これには、恐怖、不安、ストレス、イライラ、うつなど、心理的な影響が含まれます。
痛みの知覚は、単に体の感覚だけではなく、感情や思考が深く関与しているため、個人によって痛みの感じ方は異なります。
心理的な要因が痛みの強さや持続時間に大きく関わるため、痛みの知覚は物理的な損傷だけでなく、心理的、社会的な要因に深く影響されます。
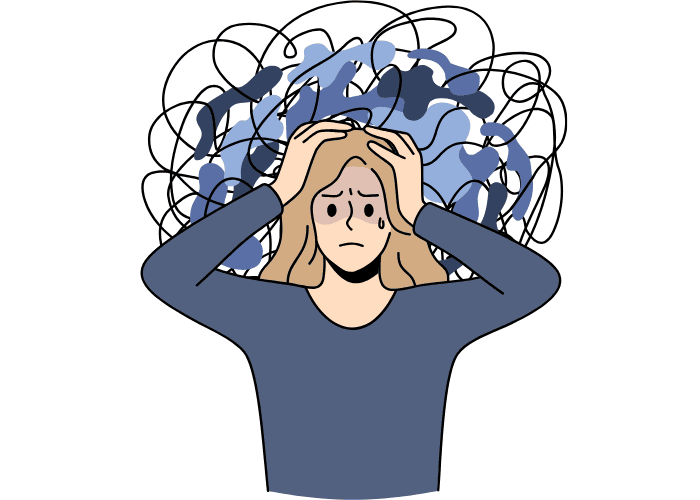
「個人的な体験」とは?
痛みは「生物学的」「心理的」「社会的」要因によって異なる体験として感じられます。
そのため、痛みの感じ方やその強度、質、耐性は人によって大きく異なります。
生物学的要因
痛みに対する感受性や耐性は人によって大きく異なることが知られています。例えば、同じ痛みの刺激を受けた場合でも、ある人は強く感じる一方で、別の人はそれほど強く感じないことがあります。
痛みに対する感受性の差は主に「神経系の構造」「免疫系の反応」「内分泌系の反応」によって左右されることがわかっています。
これにより、同じ刺激に対する反応が個人差を生むのです。
神経の構造と機能
脳や脊髄などの神経系の構造や機能にも違いがあり、これが痛みの知覚に影響を与えます。
例えば、「神経障害性痛(神経自体の損傷や異常)」がある人は、痛みを過剰に感じることがあり、逆に神経伝達が抑制されると、痛みを感じにくくなることがあります。
神経の機能の一つである神経伝達物質のバランスや働きが痛みの感じ方に影響します。

例えば神経伝達物質のエンドルフィンが不足していると痛みを和らげる力が弱まり、逆に痛みを強く感じることになります。
さらに、神経系の過敏性が高い場合、通常の刺激でも強い痛みとして感じることがあります。
慢性痛のような状態では、神経が過剰に反応して、軽い刺激でも強い痛みを感じることが多いです。
免疫系の反応
免疫系の反応も痛みの知覚に関連します。炎症が発生すると、体内でプロスタグランジンなどの化学物質が分泌され、神経受容器を刺激して痛みを引き起こします。
免疫系が過剰に反応していると、痛みの感受性が高まることがあります。
自己免疫疾患や炎症性疾患が痛みを強く感じさせる原因となることもあります。

内分泌系の反応
ホルモンの変動も痛みの感受性に影響を与えます。
特に女性は月経周期や妊娠、閉経などによるホルモンの変化により、痛みを強く感じることがあります。
ストレスホルモンであるコルチゾールが高いと、痛みに対する感受性が高まり、逆に痛みが強く感じられることがあります。
心理的要因
痛みの感じ方は、「精神的な状態」にも大きく影響されます。心理的な要因としては、「ストレス」「不安・恐怖」「うつ状態」などが挙げられ、これらが痛みの知覚を増強することがあります。
ストレスの影響
ストレスや不安は、痛みの知覚に対して増強的な影響を及ぼします。これらの精神的な状態は、身体の神経系に過剰な刺激を与え、痛みを強く感じさせる原因となります。
ストレスがかかると、身体は交感神経系が活発になり、「闘争・逃走反応(fight or flight response)」が引き起こされます。
この反応により、コルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されますが、これらのホルモンが神経系を過敏にし、痛みに対する耐性を低下させます。
結果として、普段はそれほど痛みを感じない刺激でも、強く痛みを感じることがあります。

ストレス状態が長期間続くと、「痛みの閾値(痛みを感じる最小の刺激)」が低くなることが知られています。
痛みの閾値が低くなるというのは痛みを感じやすくなるということです。
不安の影響
不安が強いと、脳が痛みを過剰に予測することがあります。
これは、痛みの知覚に関与する脳の領域(前帯状皮質や扁桃体など)が過敏になり、痛みを大きく感じさせる結果になります。
不安が強い場合、痛みの予測や過剰な反応を引き起こし、その痛みをより強く感じることがあります。
冒頭で解説したノシセプションが過剰に起こるということになります。
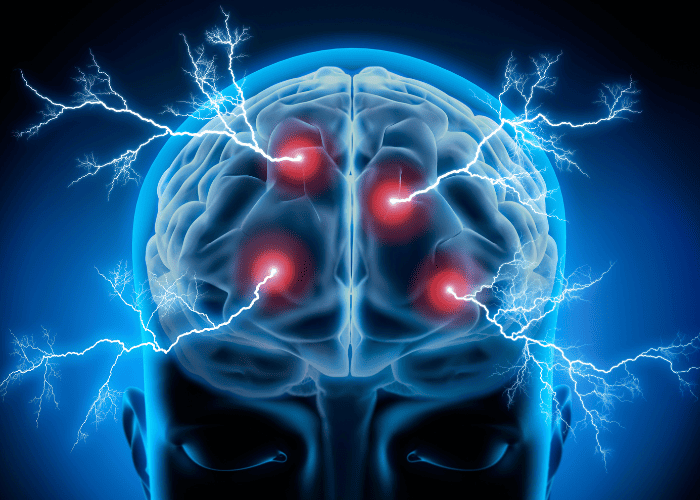
神経系が過敏に反応することで、痛みの感覚が増強されるのです。
恐怖と過去の経験
痛みの過去の体験が恐怖や不安として再び浮かび上がり、その後の痛みの知覚に強い影響を与えることがあります。これを「痛みの条件付け」と呼びます。
痛みの条件付けと恐怖
過去の痛みが恐怖として記憶に残り、それが再び痛みを感じたときに強い反応を引き起こすことがあります。
例えば、手術や治療の痛みがトラウマとなり、その後同じ部位で痛みを感じるたびに強い恐怖が生じます。
この恐怖が痛みを増強させる要因となります。
心理的なストレス反応として「恐怖回避反応」が起こり、痛みを感じる際の反応が過剰になり、痛みの強度を増すのです。

特にコンタクトスポーツをしているアスリートなどに多く見られることがあります。
同じシュチュエーションになると痛みが起こる。また同じシチュエーションになるのが怖くて痛みが取れない。などです。
恐怖と痛みの認知の変化
恐怖感が強いと、脳は痛みの予測に対して過剰に反応し、「痛みを恐れる」あまり、実際の痛みよりも痛みを強く感じさせる場合があります。
これが慢性的な痛みに繋がることが非常に多いパターンです。
うつ状態
うつ状態は、痛みに対する感受性を高めることが知られています。うつ状態では、神経系の働きが変化し、痛みの知覚が増加する傾向にあります。
最近の研究では、慢性痛患者さんとうつ病患者さんの脳のMRIを撮影すると、脳の萎縮の仕方がかなり似た形になると言うことがわかっています。
ここで言う「うつ状態」とは、うつ病を指すわけではありません。

精神的にうつ気質になってしまうと言うニュアンスで捉えてください。
うつ状態と痛みの感受性
うつ気質の患者さんでは、神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンのバランスが崩れ、これが痛みの知覚を強化します。
神経伝達物質の不均衡が、痛みに対する感受性を高め、「痛みの閾値が低下」するため、普通の刺激でも強く痛みを感じることがあります。
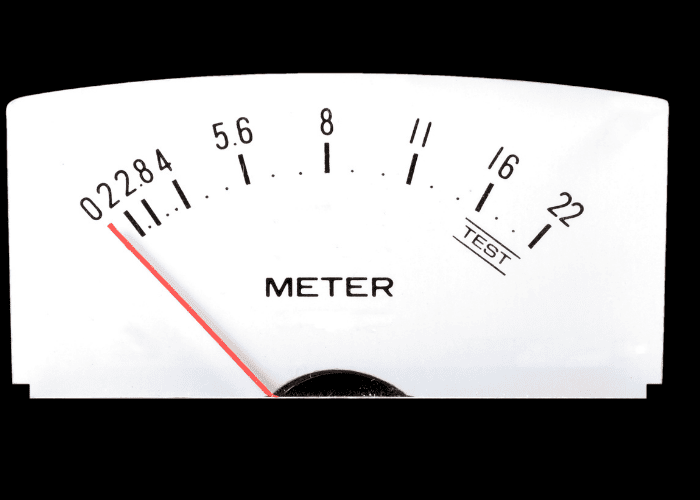
慢性痛の悪循環
うつ状態の患者さんでは、慢性痛が悪化しやすい傾向があります。
慢性的な痛みが続くことで、精神的なストレスや不安が強化され、逆に痛みを感じやすくなることがあります。
このように、「痛みとうつ状態の相互作用」により、痛みの管理が非常に難しくなることがあります。
脳の痛み処理系の変化
うつ状態にあると脳内での痛みの処理を担う領域に影響を与え、前頭前野や帯状回などの領域が痛みに対して過敏に反応します。
これにより、痛みの感覚が過剰に増強され、うつ状態と痛みが相互に悪化することがわかっています。
社会的要因
痛みに対する認識や反応は、個人の「文化的背景」「社会的状況」に強く影響されます。痛みにどう反応するか、どのように表現するかは、社会や文化により異なります。
文化的背景
文化的背景は、痛みに対する反応や表現に深く関与しており、各文化における「痛みの認識」や「表現の仕方」は異なります。文化的な要因は、痛みをどのように感じ、どのように表現するかに大きな影響を与えます。
痛みの表現
ある文化では、痛みを外に表現することが奨励される場合もあれば、逆に痛みを内に秘めて我慢することが美徳とされる場合もあります。
この文化的な違いが、痛みに対する認識やその知覚に大きく影響します。
特に日本の場合は痛みを我慢して何かを成すことが美徳と感じられることが多いです。
例えば、ぎっくり腰でも仕事に行かなければいけない。などが挙げられます。
これまでの話が理解できていれば、このぎっくり腰による強い痛みを我慢しながら仕事を行うことが慢性腰痛につながっていってしまうことが想像できるかと思います。
耐える文化(忍耐文化)
例えば、日本や多くの東アジアの文化では、痛みを表に出さずに耐えることが重視されることが多いです。
このような文化では、痛みに対する反応が抑制されることがあり、表面的には痛みを感じていないかのように振る舞うことが求められる場合があります。
心理的にこれを「痛みの抑制」と呼びます。
痛みを外に表現することを避けることで、社会的なプレッシャーや恥の感情から守られる一方で、痛みの心理的影響が増加することがあります。

表現を奨励する文化
一方で、西洋文化や一部のラテンアメリカ文化では、痛みを表現し、他者に助けを求めることが社会的に受け入れられることがあります。
このような文化では、痛みを訴えることが許容され、治療や支援を受けることが奨励されます。
痛みを表現することで、痛みの管理やサポートが得やすくなる一方で、過剰に痛みを訴え続けることが社会的に問題視される場合もあります。
痛みに対する社会的態度の違い
痛みにどのように向き合うか、どの程度痛みを受け入れ、処理するかは、個人が育った文化や社会環境によって異なります。
痛みを「治療の対象」として捉える文化もあれば、「試練や成長の一部」として捉える文化もあります。
これらの文化的な考え方が痛みに対する心理的な反応に影響を与え、痛みの強度やその持続時間に関与します。
例えば、幼少期に怪我をした際、過剰に反応してしまうご両親であった場合、大人になってからも痛みに敏感になってしまう傾向があります。
逆に、怪我をしても「放っておけば治る!」と言われてきた方は、大人になっても痛みに敏感になる傾向は少ないです。
どちらにもメリットデメリットはあります。前者の場合、痛みに対する恐怖心から慢性痛へ移行しやすく、後者の場合、痛みに対して鈍感がゆえにリミッターを知らず、痛みが長引く傾向があります。
社会的サポート
社会的なサポートとは、家族、友人、職場の仲間などから受ける支援、また医療従事者からのサポートなどのことです。
心理学的には、「社会的支援」があると、痛みに対する心理的な負担が軽減され、痛みの知覚が和らぐことが知られています。
心理的安定
サポートがあると、痛みに対する不安や恐怖が和らぎ、「ストレス反応が軽減」します。
ストレス反応が軽減されることで、痛みの強度が低く感じられることがあります。
特に、サポートを受けることで、脳の痛みを処理する領域(例:前頭前野、帯状回)における活動が変化し、痛みの知覚が軽減されることがあります。
前頭前野や帯状回は脳の痛みの処理系の上の項目で解説しております。忘れてしまった方は再度読み返してみてください。
エンドルフィンの分泌
社会的な支援があると、「エンドルフィン(脳内の自然な鎮痛物質)」が分泌されやすくなり、痛みの感覚が和らぎます。
社会的支援は、心理的にポジティブな感情を引き起こし、痛みを和らげる神経生理学的なメカニズムを活性化します。
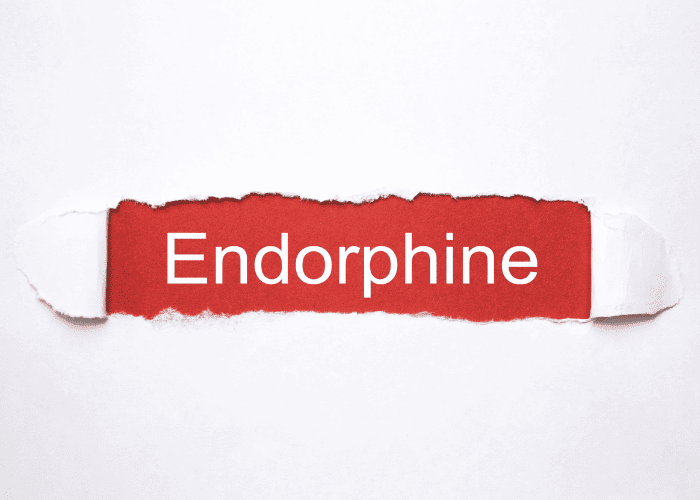
孤立と理解の欠如
逆に、社会的な孤立や痛みに対する理解がない環境では、痛みが増大することがあります。
孤立していると、心理的なストレスが増し、「痛みの認知の強度」が増すことがあります。
社会的な支援が得られない環境にいると、痛みに対する不安や恐怖が増幅され、痛みが強く感じられます。
これは特に高齢者の方の多く見られるパターンです。できるだけコミュニティに参加して多くの方と接点を持つことが痛み軽減につながります。
孤立状態では、痛みを感じること自体が精神的なストレスとなり、痛みの感覚をさらに強化することがあります。
また、周囲の人々から痛みへの共感が得られない場合、患者が感じる痛みの「社会的孤独感」が増し、その結果として痛みが持続的に悪化することがあります。
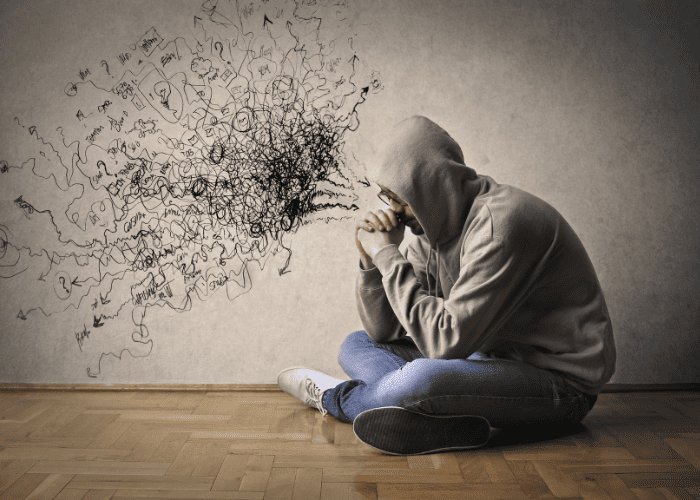
社会的理解の欠如
特に職場や学校、家族内で痛みに対する理解が不足している場合、痛みを抱える人は自己の症状を軽視されたり無視されたりすることがあり、それが心理的なストレスとなり、痛みの感覚を強くすることがあります。
このループにハマってしまうと、気持ちはうつ状態に陥ってしまいます。その先の結果については前項で解説した通りです。
忘れてしまった方は再度上に戻って読み返してみてください。
痛みについて知る【痛み学基礎2】まとめ
長文お疲れ様でした。少し難しい話でしたがよく頑張って読み進めていただきました。
痛みは単なる感覚だけでなく「感覚的」「情動的」「社会的」な側面が絡み合った非常に複雑な体験であることが理解できましたでしょうか?
国際疼痛学会(IASP)の定義には、痛みは、実際の組織損傷やそのリスクと関連しているだけでなく、それが感覚的であり、同時に感情的な反応を伴うこと定義されています。
さらに、痛みは個人的な体験であり、その感じ方は生物学的、心理的、社会的な要因によって大きく異なることもお分かりいただけましたでしょうか?
腰痛にしても、膝痛にしても、股関節痛にしても、体に起こるすべての痛みの治療には、「生物学的」「心理的」「社会的」要因を総合的に考えて個別的なアプローチを行うことが非常に重要です。
痛みとはこれだけ複雑であるからこそ、痛み止め、湿布、外科的手術だけでは当然改善できないことの方が多いですし、単に凝り固まった患部をもみほぐす、鍼をする、骨盤の矯正をするなどの治療でも改善できないのです。
痛みは常に主観的であり個体差があるのですから、我々治療家があなたの内側にあるものを引き出しながら治療をしてくことで改善へ一歩一歩歩みを進めることができるのです。
また痛み学の1回目にもお伝えしましたが、痛みは実態のない怖いものではありません。
今回のコラムを読んでいただき痛みの実態がなんとなく把握できたと思います。
そして次回が最終回となります。
痛みの定義には実は「付記」というおまけがついています。
今回の内容をしっかりと理解していただけたら、次の最終回に進んでくださいね。
関連記事
当院で治療した患者様の声

椎間板ヘルニアの症状が改善しました!
症状:腰椎椎間板ヘルニア
仕事中にも痛みがあり常に太ももから足全体に痺れもありました。
外科では痛みとめと湿布を出され手術しか痛みは取れないと言われていました。
どうせ変わらないだろうと思い治療をしてもらいましたが治療後びっくりするくらい痛みもなくなり、足が軽くなりました。海老野先生の説明が丁寧で痛みの原因も理解できるため前向きに治療をしたいと思えました。
外科で手術しかないよ!と言われた方、ぜひ海老野先生に相談された方がいいです!

横浜市|S.H様|30代|男性
腰と肩の痛みが改善しました!
症状:慢性腰痛、五十肩
昨年の晩秋の頃から、左肩と左腰に痛みを感じ自身でストレッチ等試みたが一向に改善せずにいた時、地元久里浜でえびの治療院開院の知らせを耳にし、 オープン日より早々受診を開始!
従来の鍼灸院だと、もちろん鍼治療は施術していただきその場は、痛みも取れスッキリするのだが2.3日経つと痛みが戻り通院の繰り返し!?
しかし‼️ここ!えびの治療院は一味違う‼️患者とのヒヤリングをしっかり行い原因はどこにあるのか見つけ出しそこをピンポイントに治療を行うので、医師からの説明を受けながらの治療なので納得して治療を受けられます。
自身も現状まだ定期的に受診しておりますが、日に日に痛みも無くなり、初診時より痛み等も格段に解消されております
身体の痛みで、諦めている方‼️一度受診してみる価値はあると思います。【Google口コミより】

腰の痛みが改善しました!
症状:ゴルフ後の腰痛
4月から通院をしています。
4年前にスポーツで腰を痛めてしまい色々な整体院や鍼灸院を探して治療を受けて来ましたが治療を受けた時は
一時的によくなるのですがすぐに痛みが出てしまい痛み止めを飲みながらの日々でした。
年齢的なものも含めて諦めかけていたときにポストに入っていたチラシを見て
正直あまり期待をしないで受診しました。
最初は1週間に一度治療を受けて通院をしていましたがふと痛みがなくなってきていることに気づきました。
治療の効果がすぐに感じることはないのかもしれませんが1ヶ月を過ぎたあたりから自然に痛みが消えていくことを実感すると思います。
今でも2週間に一回治療を受けていますがスポーツのパフォーマンスも以前以上に上がってきて自分でもびっくりしています。
同じように痛みがよくなることに諦めている方はぜひ一度受信して1ヶ月ほど通院して欲しいと思います。
先生は若い方ですがしっかりとした知識のもと日々勉強をされていると思いますので信頼できます。
【Google口コミより】
横須賀市|M.T|50代|男性

ぎっくり腰が改善しました!
症状:ぎっくり腰(急性腰痛)
ギックリ腰になってしまい、突発だったけれどその日に予約を入れて頂き治療してもらいました。動くのも辛かったので助かりました。
丁寧なヒアリングで痛みの原因を探り、
豊富な知識と経験でその人に合った治すためのアプローチをしてくれます。
初診でかなり良くなった感があったのですが、ぶり返したくないので何回か通い治療してもらいました。
その後の生活での適切な対処法も指導してくれるので、みるみる良くなり今では無事仕事も普通にこなせるまで回復しました。治してくださった先生に感謝です。
整形外科行っても湿布をくれるだけで根本的に治らない等、悩みを抱えてる人は一度治療を受けてみるのをおすすめします。
【Google口コミより】
横須賀市|t-has(has)||50代|男性

慢性腰痛が改善しました!
症状:椎間板ヘルニアによる腰の痛み(慢性腰痛)繰り返すぎっくり腰(急性腰痛)
私は腰椎ヘルニア持ちで、ぎっくり腰を繰り返してしまう状態でして、酷い時は2週間に1度の頻度でぎっくりになり、何なら歩行してる時に急になったりと、とても酷い状態で⋯次男が赤ん坊の時は全く抱っこしてあげられないという、とんでもなく辛い日々を送っておりました。
えびの先生が横須賀で開業する以前からお世話になっておりましたが、開業後は自宅から少し遠いのもあって、他の先生に診てもらったりもするも、満足いくレベルの復調とはならず⋯
えびの先生に施術してもらうと、ガチガチに固まってたのがほぐれ、調子は良くなるし、持続するしで、技術の高さを改めて実感!!以前は週1で施術頂いていたが、ここ2年程は2ヶ月に1回ぐらいのメンテナンスで、子供とも好きに遊べて、趣味のスノボや和太鼓なども問題なく出来て、何不自由無い生活をしています!
妻や友人達も腰などの不調で診てもらっているが、施術後すぐに、曲がっていた腰が伸びて、膝をあげるのもしんどかったのが走れる様になるなど、皆不思議な体験をしております(笑)
最後の砦⋯凄いです!!豪語するだけある凄い技術と、進化し続ける為に自己研鑽を惜しまず継続しているお姿に、いつも感服しております!!
身体の不調で悩んでる方、整骨院など通うも改善しない方、一度相談してみてください。最後の砦があります。

【Google口コミより】
横浜市鶴見区|富塚裕太様|30代|男性
慢性腰痛が改善しました!
症状:椎間板ヘルニア術後の慢性腰痛
こちらの治療院は半年前からお世話になっております。
私の55年の人生において、腰椎椎間板ヘルニアのオペを2回ほど経験し、人生の半分以上を腰痛と過ごしてきました。
半年前に腰を痛めてしまい、仕事もできず、どうにもならない状況の中で、スマホで探して、調べて、やっとたどり着いたのが、この治療院でした。
院長の施術を受けることで、日常生活への復帰が早期に実現したことは、院長が保有している施術技術の高さの証明でもあります。
これまで、自分自身の身体に向き合って、改善を試みるため、病院の整形外科をはじめ、整体院、接骨院、整骨院、鍼灸院などに通ってみましたが、その時その時の対処療法にしかなっておらず、自分の腰痛の根本原因がわからず、治療難民になっていました。
そんな時に、この治療院のホームページを閲覧したことで、院長のハッキリとした治療の方向性が掲載されていることから、「ここだ!」と思って連絡して正解でした。
現在は、週に1回のペースで通っていまして、私の腰痛の原因となる部分が何か所も連動していることがわかってきましたので、それらを徐々に徐々に改善していく方向で実施しています。
自身の痛みの根本的な原因がわからず、悩み苦しんでおられる方は、ぜひ、電話して予約して、診察を受けることをオススメします。
ホームページに掲載されているとおり、「最後の砦」であり「治療院」ですから・・・

【Google口コミより】
横須賀市|joecool123|50代|男性
ぎっくり腰が改善しました!
症状:ぎっくり腰(急性腰痛)
介護職と司会業、ダブルワークをしております。介護仕事中、まさかのギックリ腰!すぐに整形外科を受診し、痛み止めの薬と冷湿布を大量に処方されましたが、次の日婚礼司会を控えていたこともあり「今日中になんとか回復しないと!」という思いで、数年前、海老野先生の結婚式でお手伝いをさせていただいたご縁もあり、海老野先生に助けを求めました。幸い、すぐに連絡がつき、病院を出てそのまま海老野先生のもとへ。
病院内は車椅子。治療院への移動も介助なしでは歩けませんでした。が!!治療後、スッと立位を保ち、歩行が出来るようになりました。次の日は、いつも通り司会台に立つことが出来ました。周りの人は皆、「本当に昨日、ギックリ腰だったの?」と驚いていました。その後、完全に腰の違和感がなくなるまで、丁寧に施術をしていただいたお陰で、全く再発もなく元気に過ごしております。
先生、本当にありがとうございました!!【Google口コミより】

茅ヶ崎市|T.S|50代|女性
全身の症状が改善しました!
症状:踊りの練習による膝痛、腰痛、股関節痛、自律神経の乱れ、生理痛
踊りの大会1ヶ月前に左膝の痛みがあり、受診。
大会の事を伝えると「大丈夫です。大会までには、治せます。」と回答があった。
半信半疑であったが、週2回通った結果、1ヶ月経たない内に10年治らなかった膝が完治。
その他の猫背やスマホ首、腰痛、生理痛、仕事のストレスから来る自律神経の乱れも合わせて治すことが出来た。
控えめに言ってもここの先生は「スーパードクター」である。
現在は、メンテナンスに通う程度となり、2週に1回のペースに落ち着いている。身体と心の悩みは、こちらで治療できると思う。

【Google口コミより】
横須賀市|丸山あい様|30代|女性
全身の症状が改善しました!
症状:仕事の疲労による慢性的な肩こり、腰痛、膝痛、坐骨神経痛
首、腰、膝と痛みで身体を動かすことも辛い日々を過ごしていました。施術中はくだらない話で盛り上がり、施術後は身体の痛みは消え、とても軽くなります。最近では「痛くてどーにもならない。」という事が少なく、動いた後でも身体の痛みが出ない事が多くなり、外出する事が楽しみになっています。痛みが少なくなると、また違った身体の可動域が気になり、質問すると根本的に治していく方法をアドバイスしていただけました。どんな事を質問しても、知識に溢れているため、的確なアドバイスが聞けて、とても心強いです。
【Google口コミより】
横須賀市|Li様|50代|女性

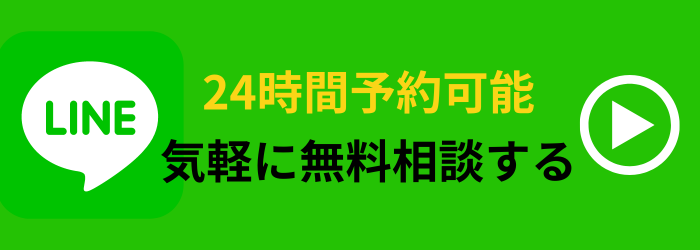
横須賀えびの治療院院長の海老野です
最後までお読みいただきありがとうございます。
専門学校入学と同時に治療業界で修行を始め13年が経ち、これまでに2万5千人以上の患者様の治療を行ってきました。
これまで数多くの病院を巡り、治療を行ってきたけれど中々改善できずにネットで色々調べてこのページに辿り着いた方もたくさんいらっしゃると思います。
ネットにはたくさんの情報が掲載されており、実施に何が正しいのかわからなくなってしまう方が非常に多いです。
痛みに対しての理解を深めることが、今あなたの体に起きている体の痛みを改善するための大きな助けになります。
1日でも早く痛みを改善できるように一緒に頑張っていきましょう!